元弘元年八月二十七日、天皇は笠置寺へ臨幸あり、本堂を皇居とせられた。比叡山東坂本の合戦で六波羅の軍勢が負けたといふ事が知れて来たので、近国の兵士が此処彼処から笠置へ馳せ集つて来たけれども、名高い武士で手下の軍勢を百騎なり二百騎なり引連れた大名はまだ一人も来なかつた。此軍勢では皇居の警固だけもおぼつかないと、天皇は御心配の中にとろ/\と御眠りになつたところ、紫宸殿の庭前に似た所に、大きな常磐木があつて緑の葉がよく匂ひ、南へさし出た枝は特に繁り蔓つてゐた。其下に三公(一)百官達が位の順序に列坐し、南へ向いた一段高い所には、畳を高く敷いた御座があつて、まだ誰れも坐つてゐない。「はて、誰れをもてなす為めであらう。」と天皇は怪しく思して立つてゐられた処へ、鬟(二)を結つた二人の子供がひよつく現はれ、天皇の御前に跪いて涙を流し、「広い国中に少しの間さへ御身を隠される所もございません。しかしあの樹の蔭に南向きの座席がございます。これは陛下の御為めに作つた玉座でございますから、暫くの間ここにおいでになつていたゞきたい。」と云つて、子供は天へ上つてしまつた夢を見られた。御夢はまもなく覚めた。
天皇はこれを天つ神が御自分にお告げになる夢だと考へられ、文字の上から色々御思案あつた所、木に南を結びつければ楠といふ字である。其蔭に南を向いた御座があり、それに坐れと二人の子供の教へたのは、御自分が再び天子の徳を治めて、天下の士を朝廷に伺候せしめる事を示されたものであると、御自分で夢判断を遊ばされて、いと心丈夫に思召された。夜が明けると、寺の衆徒、成就房の律師を呼び出されて、「此辺に楠といふ武士はゐないか。」とお尋ねになられた。「この近くにそんな者のゐることは聞きませんが、河内国金剛山の西には楠多門兵衛正成と云つて、名高い武士が住んで居りまする。」とお答へ申し上げたところ、今夜の夢のお告げは正しくそれだと思召して、天皇は「すぐ其者を呼べ」といひつけられたので、藤房卿は勅命を承り、急いで楠正成を呼び出された。正成は武士たる者の此上もない名誉だと思つて、とかうの思案もせず、こつそりと笠置へ来た。天皇は藤房卿をして、
「北條氏の征伐について、仔細あつて正成を頼まれ、勅使を立てられた処、すぐさま馳せつけてきた事は誠に感じ入る。一体如何なる謀をめぐらせば、勝を一時に決して天下を太平にする事が出来るか。それについての考へを残らず申してみよ。」
といふ仰せを伝へさせられた所、正成が畏つて申上げるには、
「近頃北条氏の大逆が天の怒りに触れましたからには、これに天誅を加へられるのは何の仔細もございません。しかし天下の平定には武略と智謀との二つが必要でございます。若し武力のみに頼り、正面から軍勢を合せて戦つたならば、日本国中の兵を集めても、武蔵、相模、二国の兵に勝つ事は出来ません。若し謀を以て戦つたならば、関東方の武力は唯だ利を摧き、堅を破るに過ぎないものです、これは欺き易く、怖るるには足りません。勝敗は合戦の習はしでございますから、一時の勝敗に重きを置かれてはいけません。此正成がまだ生きてゐるとお聞きになられたなら、御運はきつと開けるものと思召されたうございます。」
と力強く申上げて河内へ帰つていつた。
|
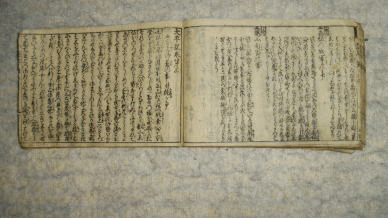
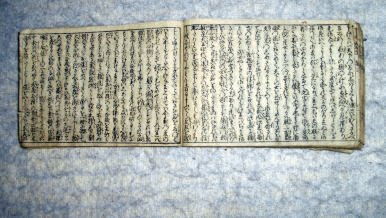
|
天皇が笠置においでになり、近国の官軍が御身方に参つてゐるといふ事が京都へ知れたので、九月一日六波羅の両検断(三)は宇治の平等院へ押し出して軍勢を集め、明二日には笠置へ攻め寄せる準備をした。所が高橋又四郎といふ者があつて、抜けがけの功名をしようと、僅か三百余騎ばかりを率ゐて笠置の麓へ押し寄せたが、忽ちの内に攻め敗られ、それに続いた小早川の軍勢も亦一度に追ひ立てられてしまつた。
そこで両検断は宇治で軍勢を四手に分け、手筈を定めて、九月二日、笠置の城に向つて出発した。其軍勢は合せて七万五千余騎にも上り、笠置の山の四方二三里の間は少しの隙間もなく兵士で充ち満ちてゐた。一夜明けて九月三日朝六時、東西南北の寄手は互ひに近づいて鬨の声を上げた。其声は百千もの雷が一時に鳴り落ちたやうで、天地も動くかと思はれた。鬨の声を三度上げ、矢合(四)をして鏑矢を射かけたが、城の中は静まり返つて鬨の声も合さず、答の矢も射かけず、人が居るとは見えなかつたので、敵はもはや逃げてしまつたものと考へ、寄手の軍勢は二王堂の前まで攻め寄せ、其処から城の中を見上げると、鎧兜に身をかためた三千余人の武士達手の軍勢一万余騎はこれをみて、進む事も退く事も出来ず、仕方なく踏みとどまつて暫くの間は睨み合つてゐたが、やがて城中より足助次郎重範が名乗を上げて、一番矢に荒尾九郎兄弟を射倒したのを手始めに、大手搦手の寄手、城の中の軍勢達は互ひに喚き叫んで攻め戦つた。
寄手の軍勢は追ひ立てられて一合戦の後には、城を攻めようと云ふ者は一人もなく、唯だ城の四方を囲んで遠攻めにした。遠攻めに日を送つてゐる処へ、同月十一日河内国から急使がきて、楠兵衛正成と云ふ者が宮方につき、兵を挙げて赤坂山に立籠つたと告げた。これは一大事だと騒いでゐる処へ、亦同月十三日の夕方に備後の国から急使が到着して、桜山四郎入道が同じく宮方について兵を挙げたと告げ知らした。目の前では笠置の城が強く、諸国の大軍勢で日毎夜毎攻め立てゝも落城しないのに、後では楠、桜山らの宮方が兵を起して、急を告げる使者が毎日々々櫛の歯を引くが如くに六波羅に着いた。六波羅の北方(きたかた)駿河守は安き心もなく、日々急使を鎌倉に立てて東国の軍勢の援けを乞うた。北條高時は大いに驚いて、「すぐさま討手の軍勢を差向けよ」との命令。
二十万七千六百余騎の軍勢が九月二十日に鎌倉を出発した。
こゝに備中の国の住人で、陶山藤三義高、小見山次郎某(なにがし)といふ二人が笠置城の寄手に加はつてゐたが、関東の大軍がもはや近江に着いたと云ふ事をきいて一族の者共を集め、
「お前達はどう思ふか、此間からの合戦に死ぬる者は数知れずあるが、皆これといふ功名も立てずに死ぬのである。同じ死ぬる命なら目ざましい合戦をして死ねば、名誉は長く残り、子孫は栄えよう。まして日本中の武士が集つて五日攻めても落す事の出来ぬ此城を、我々の軍勢丈で攻め落せば名は古今に双ぶ者なく、忠義は万人の上に輝くであらう。さあ今夜の雨風に紛れて城中へ忍び込み一夜討をかけて天下の人々を驚かさう。」
と云ふと、一族五十余人の者共は「よからう」と、賛成した。
其夜は九月晦日の事とて、物のあやめもわからぬ暗闇である上、風雨が烈しく吹いて面を上げる事も出来ない中を、五十余人の者共は背に太刀を負ひ、後に刀を差して、城の北に聳えてゐる数百丈の石壁、鳥も翔りにくいやうな所を登つて行つた。岩角をよぢ、木の根にすがり、四時ほどの間苦労に苦労をして塀の側まで辿り着き、皆塀をのりこえて、先づ城中の様子を見定めた。皇居は何処であらうと、探り/\本堂の方へ行く所を咎められたが、陶山吉次が夜廻りの者(五)だと偽つた為め免れられたのを幸(さいはひ)、其後は却つて大びらに、「それぞれの御陣に御用心下さい」と高声に呼びながら通り過ぎ、静かな本堂へ上つてみると、これこそ皇居らしく、蝋燭を多く燈し、振鈴の声が幽に聞えて来た。陶山は皇居の様子を見定めて、本堂の上にある峯に上り、人の居ない僧舎があつたのに火をつけて、一度にどつと鬨の声を上げた。四方の寄手の軍勢はこれを聞いて、それ城中に裏切者が出たと、口々に鬨の声を合せて喚き叫んだ。陶山の率ゐる五十余人の兵士は今詳しく城内の様子を見て置いた事とて、此処の役所に火をつけては彼処で鬨の声を上げ、彼処で鬨の声をあげては此処の櫓に火をつけるなど、四方八方に走り廻つて、三面六臂の働きをしたので、其軍勢が城中に充ち満ちてゐるやうに見えた。そこで陣所陣所を堅めてゐた官軍は、城中に敵の大軍が攻め入つたと考へ、鎧兜を脱ぎ捨て、弓矢を放り出して、崖、堀の区別もなく、転びながら逃げて行つた。錦織判官代はこれを見て、
「何たる見苦しさだ。天皇の身方について、武士を敵として引き受ける程の者が、敵が大勢だからとて、戦はずに逃げる法があるか。何時(いつ)のために惜む命なんだ。」と云つて、向つて来る敵に打ちかかり打ちかかり、大肌脱ぎとなつて戦つたが、矢を射つくし、太刀を折つてしまつたので、父子二人に家来十三人は、各々腹をかき切つて、同じ枕に伏して死んだ。
|







|
笠置城の火災の為め、天皇を始め奉り、宮々、卿相(六)、雲客(七)は、皆跣のまゝ足に任して、何処といふ的(あて)もなく逃げて行かれた。暫く行く内段々に別れ別れとなり、後には唯だ藤房季房の二人より外には天皇の御手をお引き申す人もなくなつた。
畏れ多くも天皇は御姿を賤しき農民の姿に変へさせられ、目指す的もなくたゞさまよひ歩(ある)かれた。其御有様は誠にあさましい事であつた。何とかして夜の中に赤坂城まで行きたいと、御心のみはあせらせたが、慣れられぬ御歩行の事とて、夢路を辿るやうな御心地で、一足行つては休まれ、二足歩んでは立どまられ、昼は道の辺の荒塚の蔭に御身を隠し、粗末な柏草を御座の敷物とし、夜は人も通らぬ野原の露をかき分けかき分け彷ひ行かれる事とて、薄い絹の御袖は乾くひまもなかつた。このやうにして夜昼三日の後に山城国多賀郡にある有王山の麓まで逃げ延びられたが、藤房季房も三日間何も食べない為め、足はだるく身体は疲れて、今はもう、どのやうな目にあつても逃げようといふ心持になれなかつたので、深い谷の岩を枕として、君臣兄弟が共にうたた寝の夢を結ばれた。
梢を鳴らす松風の音を雨が降るかとお聞きになつて、木蔭へ立寄られると、下露がはら/\と御袖にかかつた。天皇はそれを御覧ぜられ、
さして行く笠置の山を出でしより
あめが下にはかくれがもなし
(歌意──あてにしてゐた笠置の山を逃れ出てからは、天下に身を隠す所がない。「さして行く」は「指す」に笠を「さす」を云ひ懸けたもの。「あめが下」のあめは天と雨とを云ひ懸けたもの。)
と詠ぜられたので、藤房卿は涙をおさへて、
いかにせむ憑む蔭とて立ちよれば
なほ袖ぬらす松のしたつゆ
(歌意──頼りとして立寄つた木蔭でさへ、松の下露に袖がぬれる。真に頼りとする所のない世の中だ。どうしようにもいたし方がない。)
とお答へ申した。
やがて天皇は賊軍の為め見出されて、十月二日に宇治の平等院へ行幸遊ばされた。其日鎌倉の使者、大仏貞直、金澤貞将の両大将が宇治へ来て天皇に拝謁し、三種の神器を持明院の新帝(八)へ御渡し下さるやう申上げた。天皇は藤房を通じて、
「三種の神器は古より世継の君が天皇の御位につかせられる時、天皇自ら授け奉るものである。此三種の宝器を臣下の分際で勝手に新帝へお渡し申す例はまだ聞いたことがない。其上神鏡は笠置の本堂へ捨て置かれたから、きつと戦場の灰となつてゐるであらう。神璽は山中でさまよつた時木の枝へ懸けて置いたから、いつまでも我国の守となるであらう。宝剣は武士の輩が若しも天罰を考へず御体に近づき申すやうな事があつたならば、御手づから其刀の上に伏せさせられようと、片時も玉体からお放しにならない。」
と仰せられたので、鎌倉の使者両人も、六波羅の役人も、申上ぐべき言葉がなくて退出した。
天皇は三日の間平等院に御逗留の後、六波羅へ行幸遊ばされて、同月九日に三種の神器を持明院の新帝へ御渡しになられた。同月十三日には新帝御即位の儀があつた。 |




|
遙々関東から攻上つて来た大軍は、まだ近江の国へもはいらない中に笠置の城が落ちたので、皆楠兵衛正成の立籠る赤坂城に向つた。
石川河原を過ぎて城の有様を窺ふと、急拵へと見えて十分に堀もほらず、僅に塀を一重めぐらした一二町四方足らずの狭い場所へ、櫓が二三十立ちならんでゐる。此有様を見た人々は、
「何といふ可哀さうな有様ぢや。こんな域は我々の片手にのせて、投げても投げられろだらう。何か不思議な事が起つて、せめて一日でも楠に持ちこたへさしたいものだ、分捕して功名を立て、褒美にあづからう。」
と思はぬ者はなかつた。で、寄手三十万騎の軍勢は、攻め寄せると共に皆同じく馬を走らせ走らせ、堀の中へ飛入り、櫓の下に並び立つて、我先きに攻め入らうと争つた。
正成は元来智謀の人であつたから、よりすぐりの勝れた射手二百余人を城中に置き、弟の七郎と和田五郎正遠とに三百余騎をつけてよその山に備へて置いた。寄手はそんな事とは少しも知らず、唯だ一揉みに揉み落さうと、一度に四方の崖の下まで押し寄せた処を、櫓の下や狭間(九)の陰から鏃を揃へて絶え間もなく射かけたから、一時の間に千余人の死傷者を出した。関東勢は当(あて)がはづれて、
「いや/\此の様子では、一日や二日に城は落ちないぞ、暫くの間陣所々々を取り、役所を設け、手分をして戦へ。」
と云つて、攻口を少し退き、馬の鞍をおろし、甲胃を脱いで、皆幕の中で休んでゐた。楠七郎、和田五郎の二人は遠くの山からこれを見下して、「よい頃だ」と、三百余騎を二手に分け、東西の山の木蔭から菊水の旗を二本松吹く風になびかせて、静かに馬を歩ませつつ、煙、靄をまき起して攻め込んだ。関東勢はこれを見て敵か身方かと怪しみ、ぐづ/\してゐる処へ、三百余騎の軍勢が両方から鬨の声をどつと上げて、雲霞のやうに群つてゐる三十万騎の中へ魚鱗懸りの陣(一〇)をつくつて攻め入り、東西南北に割り込み、四方八方に斬つて廻つたから、寄手の大軍はぼんやりして陣を作る事も出来なかつた。又城中では三つの門を一度に開き、二百余騎が鋒を並べて打つていで、弓をひきしぼりひきしぼり残る隈なく射かけたので、さしもに大軍の寄手も僅の敵に驚いて、つないである馬に乗つてあふり立てたり、弦をはづした弓に矢を番へて射ようとしたり、又一つの甲冑に二三人も縋りついて、「俺のだ、人のだ」と引張り合つてゐる間に、主人が殺されても家来は知らず、親が討たれても子は助けず、蜘昧の子を散らすやうに石川河原へ引退いた。
関東勢は最初の合戦に負けたので、楠の武力侮り難いと思つたか、吐田(はんだ)楢原(ならはら)あたりまで押寄せたが、それから先きには進まうとする模様もなく、其処に暫く留つて、土地の様子をよく知つた者を先頭に立てゝ、後詰(ごづめ)のないやうに山を刈り、人家を焼き払ひ、安心して城を攻めようなどと相談してゐたが、本間、渋谷の手下の者に、親が討たれたり、子が討たれたりした者が多かつたから、「生きながらへてどうしよう、縦へ我々の軍勢だけでも、馳せ向つて討死しよう。」といきり立つたので、皆これに励まされ、我も我もと馳せ向つた。今度も亦押寄せると同時に堀の中や崖の下まで攻め込み、逆茂木(一一)を取りのけて進み入らうとしたが、城中には物音一つしない、これはきつと昨日のやうに、弓の上手にたくさん射かけさして浮足立つた処へ後詰の軍勢を出して攻めるつもりだらうと考へ、寄手は十万余騎を分けて後の山へ向はしめ、残る二十万騎は群をなして城を取巻いて攻めたてた。それでも城中からは一本の矢も射ず、人が居さうにも見えなかつたので、寄手は益々調子づき、四方の塀に手をかけて跳り越えようとした処を、もと/\塀は二重に作り、外の塀は切つて落すやうに拵へてあつたので、城中では四方の塀の釣縄を一度に切り落したから、塀に取りついてゐた寄手千余人はその下敷となり、目ばかり動かしてゐる所へ大木、大石を投げつけ投げつけ打ち下したので、寄手は又今日の合戦にも七百余人討たれてしまつた。
関東勢は二日の合戦に懲り懲りして、今はもう城を攻めようとする者が一人もなく、近くに陣をとつて遠攻にしてゐたが、余り引込み思案に守つてゐるのも意気地がない。四町四方にも足りない平城(一二)に四五百人の敵が立籠つてゐるのを、関東八箇国の軍勢が攻めかねて、見苦しくも遠攻にしたなどと、後々まで人に笑はれるのは残念だ。前には気が勇み立つてゐた為め楯も持たず、攻め道具も用意せずに攻めたからこそ失敗したのだ。今度は手段を変へて攻めようと、皆一人々々持楯(一三)をもち、其表面にいため皮(一四)をつけて容易に討たれぬやうに作り、それをかざして攻めたてた。崖の高さも堀の深さもいくらもないから、走りかかつて塀にとりつく事はわけないと思つたが、此塀も亦釣塀ではなからうかと危んで、容易にはとりつかず、皆堀の中におりて水につかり、熊手を塀にかけて引張つたので、将に引破られさうになつた時、城中から柄の一二丈もある長い杓に熱湯の沸き立つてゐるのを酌んで浴せかけた為め、兜の天辺の穴や鎧の肩の所から熱湯がさしこみ、身体が焼け爛れて、寄手の者は我慢が出来ず、楯も熊手も打捨てゝ、見苦しくもぱつと逃げ散つた。いきなり死ぬる程ではないが、或は手足を焼かれて立ち上れず、或は身体中を焼かれて病気になる者などが、二三百人も出た。
寄手が手段を変へて攻めると、城中でも亦工夫を変へて防ぎ、今はもうどうしようもなくて兵糧攻めにしようと相談した。其後は一切戦をやめて、自分の陣所に櫓を立て逆茂木を作つて遠攻にした。楠が此城を作つたのはほんの少しの間の事で、十分に兵糧を用意してゐなかつたので、合戦が始まり城を囲まれてから、まだ二十日余りにしかならないが、城中の兵糧はもはや尽きて、今はもう四五日分を残すのみとなつた。
そこで正成は家来を集めて、敵に自害したやうに見せかけ、暫くの間この城を逃げようと云つて、城中に大きな穴を二丈ほど堀りさげ、堀の中で討たれてゐる死人二三十人穴の中に入れ、炭や薪を積んで雨風の吹きつける夜を待つてゐた。やがて待ち設けてゐた雨風の夜がやつて来たので、城中に一人だけ残し、一同は四五町逃げたと思はれる頃城に火をつけよと命じ置き、皆寄手の軍勢の中へ紛れ込んで、五人或は三人づつ別々になつて逃げて行つた。正成は二十町余り逃げのぴてから、後を振返ると、約束に違はず城の役所々々から火が揚つてゐた。寄手の軍勢は火を見て驚き、勝鬨を上げて押しよせた。焼け静まつて後城中を見ると、大きな穴の中に焼け死んだ死骸がたくさんあつた。皆これを見て、「ああ可哀想に、正成は到頭自害した。敵ながらも立派な武士の死方だ。」
と誉めない者はなかつた。
|





|
さて桜山四郎入道は備後国を半ば従へ、これから備中へ攻めて出ようか、安芸を退治しようかと考へてゐた処へ、笠置の城も落ち、楠も自害をしたといふ事が知れて来たので、一度は附き従つた軍勢も皆逃げてしまひ、今は身を離れぬ一族の者に長年仕へてゐる家来達を併せて、二十余人が残つてゐるのみとなつた。そこで桜山は人に殺されて死骸をさらすくらゐなら、自害した方がよいと、其国の一宮へ参詣をして、八歳になつた愛子と二十七歳になつた女房とをさし殺し、社殿に火をつけ、自分も腹を切つて、一族家来二十三人と共に、灰となつて失せた。
|


|
|
|
|
|
|
|
